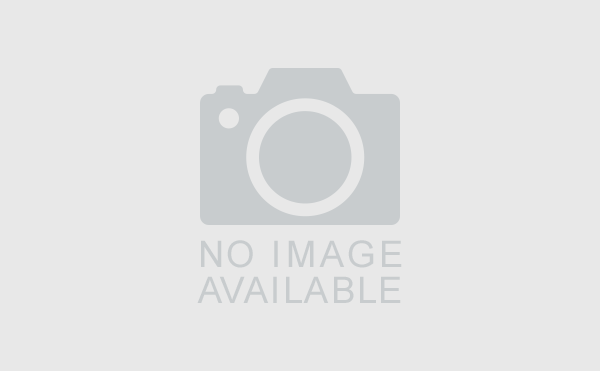2024年9月茨城県議会 予算特別委員会 江尻かな議員の質問と答弁(大要)
江尻かな議員の予算特別委員会質問と答弁(大要)
2024年9月25日(金) 茨城県議会 第3回定例会
【質問事項】
- 救急搬送における選定療養費の取扱いを変更することについて
(1)全国で前例のない県レベルでの導入の12月開始は撤回を
(2)救急医療の体制拡充を - 原子力行政について
(1)高速実験炉「常陽」と核燃料サイクル、使用済核燃料の現状 - 農業行政について
(1)主食である米を安定供給し、適切な価格で流通できる水田農業の支援
(2)有機農業の推進に向けて実践的研修・育成ができる多様な取組を
項目
1. 救急搬送における選定療養費の取扱いを変更することについて
(1)全国で前例のない県レベルでの導入の12月開始は撤回を
日本共産党の江尻加那です。はじめに、能登地方の皆様に心からのお見舞いを申し上げます。再建への希望が絶たれることがないように、支援の継続と強化を望みます。
通告しました3項目―医療、原子力、農業について、どれも命や安全、将来世代への責任を問う問題として、知事及び部長に質問いたします。
初めに、救急医療についてです。
知事は7月26日、救急車で運ばれた患者でも、緊急搬送の必要性がなかったと医師が判断した場合、病院が7,700円以上の選定療養費を患者に請求できるようにすると突如発表しました。原則無料の救急搬送を一部有料とするもので、県レベルでの実施は前例がありません。
県は、対象となる一般病床200床以上の25の大病院に呼びかけ、3病院※は実施を見送るとしています。
※ひたち医療センター(日立市)、古河赤十字病院・友愛記念病院(古河市)
そもそも、7月末に発表し、わずか4か月後の12月開始というのは余りにも一方的です。選定療養費そのものを知らない県民もたくさんいます。
先週19日の県議会保健福祉医療委員会でも、徴収する基準や苦情への対応、訴訟のリスクまで多くの懸念が議員から出されました。
私が何より懸念するのは、県民が救急車を呼ぶのを躊躇することになるのではないかということです。つくば市では、高熱を出した子どもの親が救急車を呼んだのに搬送されず、障害が残ったと大問題になっています。救急隊でも緊急性の判断は難しいのに、一般の人なら尚更です。
医療現場が今大変なのは、医師も看護師も病院も少ない本県の医療体制の問題であり、お金を徴収して救急搬送を減らそうというやり方は間違っていると思います。
そこで12月からの実施は撤回するよう知事に強く求めますが、お答えください。
【知事】
現在県内の医療機関においては、救急車で搬送された患者を緊急性の高い患者と見なし、緊急性の有無を問わずに一律に選定療養費を徴収しないという運用がなされております。しかしその結果本県では、選定療養費制度の目的である医療機関の規模や機能に応じた役割分担が十分に機能しない状況となり、救急搬送者の6割以上が大病院に集中し、そのうち軽症患者が約半数を占めております。
その中には、本来であればかかりつけ医などを受診すべきと思われる緊急性の低い方や、 包丁で指先を切って血が滲んだだけのような明らかに緊急性が認められない方も含まれております。さらに、本年4月からは医師の時間外労働の上限規制が強化された影響により、救急診療を縮小する医療機関もみられるなど、救急医療現場がさらに逼迫しております。
このままの状況が続けば、真に救急医療を必要とする緊急性が高い患者に対し適時適切に医療を提供できず、救える命が救えなくなる事態も懸念されます。このため県では、医療機関の役割分担をあらためて徹底し、救急医療体制を維持することが喫緊の課題であると考え、厚生労働省をはじめ県医師会や対象病院、消防機関に加え、郡・市医師会や救急告示医療機関などとも慎重に協議を重ねてまいりました。
その結果、救急車要請時の緊急性が認められない場合に限り、救急搬送患者からも選定療養費を徴収するという運用の基本方針について関係機関の合意が得られたことから、本年7月26日に私自ら発表したところです。
運用開始の時期については、県民や関係機関への十分な周知期間を確保しつつ、救急搬送のピークとなる冬の時期に間に合うよう、今年12月1日開始を目途とし、関係機関とともに準備を進めているところであり、運用開始方針の撤回は考えておりません。
また、運用開始以降も県民や関係機関に混乱や問題が生じないよう、救急や医療の現場の運用状況をチェックし、定期的に関係機関と検証を行いながら適切に運用できるように見直しをおこなってまいります。県といたしましては、重篤な患者の受け入れなど大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持できるよう引き続き関係機関と緊密に連携しながら県民への丁寧な説明と周知・啓発に取り組んでまいります。
【江尻委員】
知事は今、「関係機関と慎重に協議を重ねた」「合意を得られた」と述べましたが本当でしょうか。7月に県が医療機関にオンライン説明会を開いた際、「実施の根拠が不明確」「医師会員だが初めて聞いた」「責任は県がとると言うが、結局は現場責任になってくる」などの意見が出ましたが、「納得いく回答はなかった」「“説明しました” “聞きました”でフィードバックがない」と話す関係者もいます。加えて、難病患者の皆さんや介護施設、障害者の方々の声はまったく聞いてないのではないでしょうか。
知事は、運用の理由を2点述べました。一つは、救急搬送の6割が大病院に集中して大変だと言います。
そこで、資料1をご覧ください。
2次救急を担う本県75病院のうち、25の大病院に病床の6割があることをみれば、救急搬送の6割がここに来るのを問題だと言えるのか。
第二に、救急搬送の半数が入院に至らない軽症であるとも言いますが、全国も同じく半数が軽症です。
では、茨城県は救急搬送が他県より多いのか。これも人口当たりでみれば、茨城は千人当たり46件で、全国平均の49件より少ない状況です。
それなのになぜ、全国で前例のないことを本県で始めるのか、知事に再度お聞きします。端的にお答えください。
【知事】
今回の救急搬送における選定療養費の見直しは、本県の救急医療体制が逼迫し、重篤な救急患者を受け入れるという病院本来の役割を果たせなくなる事態を回避するために準備を進めているものであり、他県と比較して行うというものではございません。
他県が取り組んでいないからといって本県がいち早く取り組めないのであれば、緊急性が低い救急搬送のために重篤な患者の救急搬送が遅れ、その命が危険に晒されるという状況を放置することになります。もしそれが共産党としてのお考えなら、断じて受け入れることはできません。
今回協議を行った対象医療機関の中には緊急性の低い救急搬送患者からの徴収について、以前から独自に検討を始めていたところもあり、本県の救急医療現場の逼迫は想像以上に厳しい状況にあると認識しております。
緊急性の低い患者は本来であればかかりつけ医などを受診すべきであり、今回の選定療養費の取り扱いの見直しにより、とりあえず救急車で大きな病院の救急外来を受診するのではなく、まずは地域の診療所などの一般外来を通常の時間に受診し、必要な場合には大きな病院に紹介するという医療機関の機能分担と相互連携をさらに推進することが重要と考えます。
県民の皆様にも、医療機関の機能分担・相互連携の推進は本県の救急医療を守るために早急に対応すべき喫緊の課題であることをご理解いただけるよう、広報・リーフレットなどにより丁寧に周知・啓発を行ってまいります。
【江尻委員】
救急体制が逼迫しているというのはやはり本県の医療体制の不十分さが根本原因ではないでしょうか。「とりあえず救急車」という一部の人のことをとって全体の救急搬送が必要な方々を躊躇させるようなことがあっていいのかと言っているんです。特に、子どもさんやひとり親家庭、難病患者の方、妊婦さん、そういった方の声は知事はお聞きになったんでしょうか。
【知事】
この選定療養費の徴収の目的としては例えば、明らかに緊急性の低い切り傷であるとか擦り傷であるとか、そういうものもタクシー代わりで救急車だから無料で呼んでしまう方がいると、そういう人たちのために重篤な患者の救急搬送を犠牲にすることはできないというところから始まっております。救急車で搬送しないということではありません。軽症なら選定療養費をいただくことになりますということです。それに反対する趣旨が私には理解できません。
【江尻委員】
まず県がやるべきことは中小を含め、大病院であっても医師や看護師の体制が不十分、また地域によっては二次救急の病院さえもきちんとない。先ほど午前中の質疑でも日立おおみか病院が閉鎖されることになったと。そういう病院への支援拡充こそ必要だと、私はまずそれをやるべきではないかという趣旨でございます。ですから、体制の拡充こそ必要だということについて、次に保健医療部長に伺いたいと思います。あらためて12月からの実施は撤回するよう求めたいと思います。
(2)救急医療の体制拡充を(保健医療部長)
次に救急医療体制の拡充について、保健医療部長に伺います。部長は、本県の鹿行地域にあった「なめがた地域医療センター」で、199床あった入院機能が閉鎖されてしまったことをご存知でしょうか。救急搬送は土浦協同病院へと、県もそれでいいんだと閉鎖を認めてしまいました。患者はやむなく遠くの大病院に搬送されている現状です。地域の救急体制が不十分。選定療養費の徴収の前に検討しなければならない本県の課題は数多くあると考えますが、体制の拡充について部長の所見を伺います。
【保健医療部長】
本県においてはこれまで、初期、二次、三次救急医療機関における救急医療体制を総合的体系的に整備してまいりました。特に、重篤な救急患者に適切な医療を提供するため、ドクターヘリの運行、それを補完するような防災ヘリの運行、筑波大学附属病院の高度救命救急センター化などに取り組んでまいりました。
一方で、中小規模の医療機関においては、県内を11の地域に分けまして、輪番制などによる救急医療体制を確保しているところでございますが、救急搬送件数の増加に加え、本年4月から医師の時間外労働の上限規制、いわゆる「働き方改革」が施行された中で、受け入れ機能を向上していくことは県としては努力しておりますが、これまで以上に難しい課題になっているという認識でございます。
このため県では、休日夜間帯は救命救急センターや輪番制病院の中でも、地域の中核となる医療機関が受け入れ、翌日の日中などに重症度に応じて適切な医療機関へ円滑に再搬送ができるよう、中核医療機関への県単位のコーディネーターの配置を拡充するとともに、医療機関間の定員搬送調整のデジタル化を進め、中核医療機関の救急受け入れ体制を確保してまいりました。
また、救急搬送時間の短縮を図るため、消防機関と医療機関が救急搬送における情報を共有する県救急医療情報システムにあらたな機能を導入することにより、救急搬送の効率化を推進することとしております。具体的には、今年12月の稼働をめざしまして、救急隊が現場でOCR機能により免許証などから読み取った患者情報を患部などの写真とともに医療機関と共有する機能に加えまして、医療機関の手術室や処置室の空き情報を看護師などがスマートフォンなどでも手軽に更新し、救急隊と共有する機能などを盛り込んだシステムを構築してまいります。
さらに、「第8次茨城県保健医療計画」において、人口減少少子高齢化など社会構造が急速に変化していく中で、あらたに県域を3県域に分けた医療提供県域を設定したところでございます。これに基づいて、今回議題になっている救急医療など高度医療については、より広域的な視点に立って、どこに医療機能を集約していくか、また休日夜間の比較的軽傷な患者に対応する初期救急診療をどう充実していくか、医療機関相互の役割分担をどう進めるか、こういった協議を進め、その上で救急医療体制の整備を検討してまいります。
県といたしましては、救急医療を取り巻く厳しさを増している現況下において、救える命が救えなくなる事態、これを回避するため、デジタル技術を効果的に活用しながら、救急医療体制の充実を図るとともに、救急搬送における選定療養費の運用も含めてしっかりと準備を進めて、県民の安心安全に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
【江尻委員】
県としての課題解決という中で、やはり地域の救急医療を担う医療機関への支援という点で県が同時に行っているのが運営費補助金というものがあります。1施設当たり年間5万円、1件救急を受け入れれば620~970円。どちらも桁が一桁足りないんじゃないかと思うところですが、6年間据え置かれております。こういった運営費補助金の増額は考えているのかお聞きします。
【保健医療部長】
現況、救急告示医療機関への県単独の運営補助事業でございますが、救急の患者を受け入れたことによる医療機関の報酬はこの補助事業だけではなく、診療報酬と合わせて医療機関の経営状況をみるものでございますので、 現時点では現行の補助基準を維持しつつ医療機関の声も聞きながら検討してまいりたいと思います。
【江尻委員】
県の補助金の増額は考えていないということですけれども、この選定療養費の運用の見直しというのは救急医療の仕組みを大きく変えてしまうものです。徴収の基準も未だ不明確。医師の判断基準も示されていない。子どもやひとり親家庭、難病患者のみなさんはどうなるのか、そういった声をもっともっと聞くべきだと思います。あらためて選定療養費の徴収は県としてやるべきではない、あまりにも拙速だということを申し上げて次の質問に移ります。
2.原子力行政について
(1)高速実験炉「常陽」と核燃料サイクル、使用済核燃料の現状
2点目に原子力行政について伺います。知事は9月6日、大洗町の高速実験炉「常陽」の再稼働を了解してしまいました。今後、工事は本格着工、再来年再稼働予定です。「県議らの異論もないから了解を決めた」と言っていますが、意見を聞いた県の原子力審議会に入る議員5人は全員自民党です。再稼働に反対してきた日本共産党として強く抗議します。
そもそも根拠のない次世代原子炉の燃料として、原発の使用済燃料からプルトニウム混合燃料をつくる。その開発のための「常陽」は、核燃料サイクルの破綻を認めようとしない国策のまさに象徴です。
知事は、核燃料サイクルは破綻していると考えていないのか伺います。
また、東海第二原発にも大量の使用済燃料があり、再稼働すればさらに増えますが、青森県に持っていけば済むと考えているのでしょうか。しかし青森県でも、持ち込んだ燃料は再処理して、最後は県外に運び出す。残る高レベル廃棄物は青森では引き受けないとして、国や電力会社と7つの確約書を交わしています。福井県も同様です。
では、本県は、使用済燃料の処分について確約したものがあるのか、合わせて知事に伺います。
【知事】
国の原子力政策におきましては、高速炉開発を含めた核燃料サイクルの推進を基本方針とし、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化の観点などから、再処理やプルサーマルを進めるとされており、安全の確保と国民の十分な理解を大前提に国の責任で進めていくべきものであると考えております。
なお、先日開催した原子力審議会では国から原子力政策の動向などの説明を聴取した上で、高速実験炉「常陽」の意義や必要性について了承されたことを踏まえ、9月6日に原子力安全協定にもとづく「事前了解」を行ったところでございます。
次に、東海第二発電所の使用済み核燃料の県外搬出ですが、東海第二発電所の使用済み燃料の県外搬出につきましては大変重要であると認識していますことから、核燃料サイクルを推進する国に対して中間貯蔵施設や再処理工場への早期搬出に向け事業者とともに取り組むことを繰り返し要望しているところでございます。
東海第二発電所の使用済み燃料については、電気事業連合会が策定する使用済み燃料対策推進計画において、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とした上で、その搬出までの間は青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬出する計画となっております。青森県むつ市の中間貯蔵施設にはすでに安全対策工事を終え、日本原電においては使用済み燃料対策推進計画を踏まえ、現在使用済み燃料を中間貯蔵施設へ輸送し貯蔵するための容器にかかる国の許認可手続きを進めており、着実に搬出に向けた準備が進められていると認識しております。
【江尻委員】
確認ですが、日本原電と県の間で県外搬出の確約書というのはあるんですか。
【知事】
ございません。
【江尻委員】
どこかに持っていけばそれで済む問題ではないというのが、今の核のゴミの問題であり、国の責任だというだけで何もものを言わないのは知事としては県民に対してあまりに不誠実ではないかと今の答弁を聞いて思いました。
東海第二原発の再稼働に向けた工事も再来年の12月に延期されました。知事は7月の会見で、いつまでも工期を変更しない日本原電を「不誠実ではないか」と批判しましたが、なぜ2年3か月の延長なのか。失敗した防潮堤をどうするのか、原子力規制委員会の設計変更審査も終わらないのに、なぜ根拠もなく2年3か月と言えるのか。
工期延長の大きな要因の一つが防潮堤の欠陥工事でした。しかし、日本原電東海事務所の坂佐井本部長は、「設計上の問題ではなく、施工上の問題」だと繰り返し強調したようです。自分たちの設計はまともだったのに工事が下手だったと言いたいようですが、原発は多くの請負業者が入って作業します。事故防止に万全の措置を講じるのが原電の役割です。
不備があれば発見し、重大事態に至らないよう早期是正する。原因を究明して排除する。問題があれば自ら公表する。これら当然の責務が果たされておりません。果たす姿勢がないのか、能力がないのか。先日もコンクリートの検査資料を取り違えたり、昨年度は5件の火災も起こしています。このように工事や検査、管理に不備やトラブルが度重ねる根本問題はどこにあると知事はお考えでしょうか。所見を伺います。
【知事】
東海第二発電所の防潮堤の施工不備やコンクリートの検査書類の不備については、工事の途中段階で発見されたものではありますが、工事が認可を受けた設計通りに実施されているかどうかはその工事の途中で発生した不備への対応を含め、規制委員会が日常検査や使用前検査などで確認していくべきものであると考えております。
一方で、日本原電において頻発しております火災につきましては、県は昨年11月に日本原電に対して事象個別の原因究明のみならず、これまでに発生した火災全体を踏まえた火災の共通原因のより深い原因究明及び再発防止対策の検討を行うよう求めたところであります。
これを受け日本原電から、原因調査結果対策をとりまとめた報告書が提出され、その内容について本年7月に開催した県原子力安全対策委員会において、電気火災の専門家も含めてご審議をいただいたところであります。委員会におきましては日本原電からは、防火に関わる責任者の権限や点検の強化、電気設備の交換頻度の見直しなどの対策が報告され、委員会では現在考えられる対策が盛り込まれているとの評価をいただきました。
また委員会ではあわせて、日本原電に対して当該対策をしっかりと実施するよう求めたとともに、県に対して対策の実施状況をしっかりと確認していただきたいとのコメントをいただきました。県といたしましては、委員会で了承された対策が確実に実施されていることについて、今後県原子力安全協定にもとづく立ち入り調査を通じて確認してまいります。
【江尻委員】
なぜ県はいつも火災問題だけに矮小化してしまうのでしょうか。日本共産党に施工不良の告発を寄せた工事関係者が、「しんぶん赤旗」の取材にこう答えました。「現場では防潮堤工事不備の声が各所であがっていた」「上司は慌てふためき、どう隠すかに心血を注いでいた」「請負会社が集めた人材は技術者とは言えない素人集団で、取り返しがつかない状況になって専門の職人が入ってきたがお手上げ状態だった」と言います。
他にも施工不良の箇所があると新たな告発がありました。
資料2をご覧ください。
原電が認めた南北2つの基礎、その両側にある地中連続壁基礎も、同じ安藤ハザマの子会社が施工し、同様にコンクリート未充填や鉄筋変形などがあるとの証言でした。しかし、この基礎上部にはすでに防潮壁が造られて、基礎は目視できない。しかし、周囲を掘れば分かると言います。私は原電に事実確認の質問書を出しましたが、いまだ回答がありません。県にも確認を求めました。どうなっているのかお答えください。
【知事】
原子力発電所に関して、事業者の安全対策や保安管理について許認可権限を持っているのは国であり、原子炉等規制法に基づき国の許認可手続きの中で判断されるものと認識しております。あらたな施工不良についてはいまだ確認された事実ではないと認識しております。
【江尻委員】
確認された事実ではないというのは、原電は県に施工不良はないと言い切っているのですか。それともこれから確認していくということですか。
【知事】
それら工事途中の不備に関するものについては、工事の認可を受けた設計通りに実施されていることの確認は、工事の途中で発生した不備の対応を含め、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会が日常検査や使用前検査などを通じて確認するものであります。国による日常検査では検査官による現場への巡視や、請負業者が工事の途中で発見した不備、日本原電による立ち会い検査や現場パトロールを通じて報告される施工不備などの情報について書面や聞き取りなどで確認していると承知しております。
【江尻委員】
一般的なことを聞いているのではなくて、あらたな告発があった北基礎南基礎の両側にある基礎について、ここも不備があるのではないかと。それを県としても原電にしっかりと事実確認をしっかりと求めていただきたいということなんです。これについては告発がなければ隠されたままでは済まされないと思います。
そもそも、原電が議会に対して、そして県民に対してきちんと説明する責任があると思います。引き続き追及していきたいと思います。
工事は途中段階だからわからない、最後に検査すればいいということでは 一番大事な基礎の部分が見えなくなってしまう。それでいいのかが問われます。再稼働工事のために電力5社が3,500億円もの資金支援をしていますけれども、国民の電気料金となって跳ね返ってくるものです。
特に日本原電は、敦賀原発2号機においても、活断層データの無断書き換えが発覚。活断層を否定できず、原子力規制員会は再稼働を認めない、という結論です。それでも原電は諦めないとしていますけれども、安全で低廉な電力を供給するという社会的役割を放棄して、国策と原発メーカーのために再稼働にまっしぐらという状況です。
私はあらためて、このタイミングで県知事として東海第二原発の再稼働は認めないと明確にすべき時期と考えます。知事の所見をお聞きします。
【知事】
先ほどのあらたな防潮堤の不備の疑いについてですが、日本原電から鋼製防護壁の近接部の防潮堤工事における立会検査記録で、基礎を設置するために掘削した穴の深さや幅の測定結果、鉄筋の寸法などの検査記録、コンクリートの強度試験結果などの提示を受け、不備が確認されていないとの説明を受けています。念の為申し上げます。
それから、いつもの質問ではございますがお答えいたします。東海第二発電所の工事完了時期の延長期間につきましては、鋼製防護壁で確認された不具合への対応やその他工事の進捗状況などを踏まえ、日本原電が判断し原子力規制委員会などへの工事変更の届け出をおこなったものでございます。
県といたしましては、日本原電に対して鋼製防護壁の不具合への対応を含め、安全性を高めるための工事を着実に実施するとともに、その状況について県や関係市町村はもとより県民に適宜・適切に情報を提供するよう求めたところです。
いずれにつきましても、東海第二発電所の再稼働の是非につきましては、日本原電の工事完了時期によらず、実効性ある避難計画の策定と安全性の検証にしっかりと取り組んだ上で、その結果を県民の皆様に情報提供し、県民の皆様や避難計画を策定する市町村ならびに県議会のご意見を伺いながら判断してまいります。
【江尻委員】
不備はないと言っておりますけれども、少なくとも南北の大きな柱基礎、失敗したところは撤去せずにそのまま地中に残して周りを地盤改良するという変更を原電は考えているようです。しかしすぐ近くにあるB基礎C基礎も地盤改良となれば影響は免れません。2年3ヶ月でできる根拠はどこにもないと私は思うところです。知事として「いつもの」などという軽率な姿勢はあらためていただきたいと思います。この点についてはこれからも徹底追及していきたいと思っております。
3. 農業行政について
(1)主食である米を安定供給し、適切な価格で流通できる水田農業の支援
【江尻委員】
最後に、農業行政について質問します。
農林水産部長に、まず米の政策について伺います。店頭で買えない最中の9月4日、私は県に対し緊急の申し入れを行いました。その際の県の回答は、「政府の備蓄米流通を国に求めることはしない」「米の作付面積を減らしていく計画は見直さない」「9月下旬になれば新米が出てくる」という回答でした。
確かに店頭に出回りましたが、価格は高いままです。これまで長くコメ農家に赤字と減産を押し付け、不足を招いた結果の価格高騰です。特に貧困世帯や子ども食堂などを追い詰めています。
今回の異常事態は決して一過性ではないと考えます。そこで、主食である米を安定的に供給し、生産者にも消費者にとっても適切な価格で流通できる水田農業をどう実現していくのか、農林水産部長の所見を伺います。
【農林水産部長】
わが国における米の消費量は毎年10万トンのペースで減少している中、社会情勢の影響や在庫量の増減などにより需給バランスが変動し、米価が不安定な状況となっております。最近では、昨年の猛暑の影響による米の商品化率の低下や、インバウンドによる米の需要増加などにより、2023年産米については、店頭での消費者の購入に対し納品が追いついていない状況が見られました。
県といたしましては、米を消費者の元に円滑に供給していくためには国内外のコメ需要の傾向、米価を安定させていく必要があると認識しております。このため、今後も引き続き実務者ニーズに応じて契約栽培を計画的に進めるとともに、輸出用米や野菜などの高収益作物へ転換するなど需要に応じた生産に取り組むことで、米の需給バランスを改善させ、米価の安定につなげてまいります。
さらには、「茨城農業の将来ビジョン」に基づき、水田農業の収益性を高めるための構造改革として、農地のさらなる集約化に取り組み、メガファームなどの経営の大規模化や良食味米や有機栽培米などの特色ある米作りを推進してまいります。
また、委員ご指摘の通り、近年の高温の影響により米の品質低下や収量減少が発生するなど、高温による障害が一部で顕在化しつつあります。そこで、高品質米を安定的に生産するため、高温に強い特徴を持つ品種「虹のきらめき」などの普及拡大に取り組むとともに、被害を軽減する栽培技術の普及にも取り組んでまいります。
県といたしましては、米の需要や気候変動など今後の傾向をしっかりと捉え、経営の大規模化や生産性向上などにより、収益性の高い水田農業を推進し、需要に応じた米生産と安定供給に取り組んでまいります。
【江尻委員】
今の部長の答弁で、何度も「需要に応じた」という言葉がありましたけれども、そうやって国と県が一体になって減産を続けてきた結果の今回の事態ではなかったのかと思っております。
この間、さまざまな努力によって米の消費量が伸びていくんじゃないかというコメ農家さんの声もお聞きしました。今回の事態を反省して次にどうつなげていくのか、米の生産量を減らし続けたのではないかということに対して、しっかりと対策を練っていくべきだと思います。
(2)有機農業の推進に向けて実践的研修・育成ができる多様な取組を
【江尻委員】
有機農業についても、米作りの可能性が本県でも広がっていくと思います。県も有機農業推進計画で、JAS認証を得た農地を2倍(283haから2027年度に560ha)に増やす目標を掲げています。
では、その担い手をどう育成し、増やすのか。私はその方策の一つとして、県立農業大学校に有機農業の専科コースをつくってはどうでしょうか。埼玉県と群馬県の大学校では、すでに有機農業の専科コースが開設されています。
私は、「農業大県の茨城でこそ」との思いで、茨城町にある大学校の夏のオープンキャンパスに伺いました。しかし、学校内には有機JASの圃場はないとのことです。一方で、民間学校の鯉渕学園や日本農業実践学園にはJAS認証の畑があり、どちらも歴史と役割がありながら、生徒の減少など課題も生じています。もっと連携できるのではないでしょうか。
さらに、有機農業をめざす若者を指導する農家を、長野県や岐阜県のように里親として支援すること。また、地域おこし協力隊で農業に取り組む方々の意欲を生かせる支援につなげること。そして何より、有機農家を育成できる指導者の技術を向上させるが重要だと思います。
そこで、これから多様な取り組みをどう進めていくのか、部長に伺います。
【農林水産部長】
県ではこれまで有機農産物の供給力向上に向け、意欲的な経営体を支援してきたところであり、さらなる取り組みの拡大に向けては、新たに有機農業に挑戦する農業者を増やすことが重要だと認識しております。
このため農業大学校では、昨年度から有機農業教育カリキュラムを設置し、すべての学生が有機農業を学ぶこととしたほか、専修学校3校を持つ本県の強みをいかし、有機JAS認証を取得した学校圃場での現地研修会や、有機農業の専門知識を持つ教授を他校に派遣して講義を実施するなど連携を強化しているところでございます。
今後も、官民連携による教育を推進するとともに、有機農業に必要な農業機械の導入など、実践的な教育環境の整備にも取り組んでまいります。
次に、多様な方々が学べる環境づくりについてでございます。本県では、県内外の優れた経営者から理念や戦略を学ぶ「ヤングファーマーズミーティング」で先進的な有機農業者を招へいしたり、有機農業の生産技術や販売を学ぶ有機農業講座を開催するなど、さまざまな研修の機会を提供してまいりました。今後も、SNSや広報誌を活用して取り組みを周知するとともに、関係機関と連携し、多様な方々が有機農業を学べる環境づくりに取り組んでまいります。
最後に、指導者のスキル向上についてでございます。これまで県では、有機栽培技術や有機J A S制度の知識を身につけた普及指導員に有機農業指導員として育成しており、今年度からはJ Aの営農指導員等にも対象を広げ、体制強化を図っております。今後は、実証圃を活用した栽培技術の検討会を開催するなど、有機農業指導員や関係者による交流・研鑽の場を設け、さらなる指導力の強化に取り組んでまいります。
県といたしましては、「有機農業といえば茨城」とのポジション確立をめざし、農業の取り組みを拡大・推進してまいります。
【江尻委員】
ありがとうございます。有機農産物を学校給食にもっと活用し、販路の拡大をと願っております。以上で質問を終わります。
以上
2024年9月茨城県議会 江尻かな議員の予算特別委員会質問と答弁(大要、PDF)