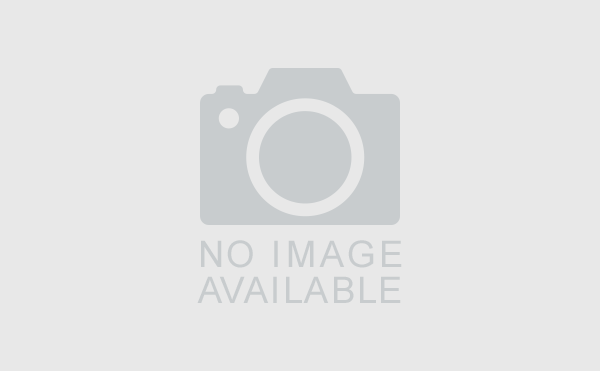2025年3月茨城県議会 江尻かな議員の一般質問と答弁(大要)
江尻かな議員の一般質問と答弁(大要)
2025年3月6日(木) 茨城県議会 第1回定例会
【質問事項】
- 県民の命を守る救急医療体制の拡充について(答弁・知事)
(1)救急搬送における選定療養費の徴収撤回・見直し - 子育てを支援する教育費の負担軽減について(答弁・教育長)
(1)学費の負担軽減のための取り組み
(2)学校給食の質の確保と無償化をめざす県の取り組み - 公共交通の維持確保と高齢者の外出支援について(答弁・政策企画部長)
(1)市町村コミュニティ交通運営への財政支援を
(2)「いばらき版シルバーパス」の創設など高齢者支援を - 水道行政と水資源開発について(答弁・知事)
(1)水道事業経営一体化の問題点
(2)霞ヶ浦導水事業の見直し - 茨城空港の機能強化案(新たな平行誘導路等)と自衛隊百里基地について(答弁・知事)
- 東海第二原発の再稼働問題について(答弁・知事)
日本共産党の江尻加那です。
大井川知事2期8年の県政運営を踏まえ、2025年度予算案や県の施策について質問します。
新年度一般会計は、県税収入も歳出規模も過去最大のもと、知事は、グローバル大企業誘致に新たに100億円の補助を創設。また、無駄な霞ヶ浦導水事業に初めて年100億を超す111億円を投入。茨城空港は平行誘導路計画まで打ち出し、自公政権と一体で大企業・大型開発に大盤振る舞いです。
一方、物価高や医療・介護・教育の負担に苦しむ県民生活への支援策は余りにも不十分で、救急搬送患者へ選定療養費の徴収も強行してしまいました。
知事の独断専行、成果・実績づくり、忖度、非公開が、パワハラや過重業務の温床になっているのではないか、検証が必要です。企業立地件数や県有施設の売却・譲渡・廃止、県立進学高校に13校も全国最多の中高一貫校をつくるなど、その下で職員や子どもたちが苦しんでいます。
県民所得についても、知事は全国3位になったと吹聴していますが、県民に実感はありません。企業所得は10年間で1.2倍に増えましたが、雇用者報酬は伸びず実質賃金は目減り。会社の儲けに対する人件費の割合を示す労働分配率も、全国平均72.4%に対し本県は64.5%と大きく下回っています。
県民の知る権利についても、74ある県審議会のうち6割(45)が非公開。東海第二原発の避難計画検証委員会や茨城空港のあり方検討会も非公開としています。私が、県日立産廃処分場建設の搬入道路について、ルートの決定過程を開示請求しても肝心部分は黒塗り。不服審査請求しましたが3年半棚上げ状態です。処分場の選定をめぐる株木建設、日立セメントなど業者との癒着の疑念に対しても、知事は「偶然でございます」と居直っています。
県民本位の県政に切り替えることを求めて、以下、質問いたします。
項目
1. 県民の命を守る救急医療体制の拡充について
(1)救急搬送における選定療養費の徴収撤回・見直し
【江尻】
はじめに、救急搬送における選定療養費の徴収についてです。
昨年7月に知事が突如発表し、12月から徴収開始。知事は1月6日仕事始めの訓示で、「全国に誇れる取組ができた」としましたが、検証会議のとりまとめがない段階で、なぜ誇れると言い切るのか。自画自賛です。昨年9月の予算特別委員会では、知事は「県が責任を取るという発言、私はした覚えがない」と答えましたが、余りに無責任です。
徴収開始から3ヶ月。資料を用意しましたので、資料1をご覧ください。
知事は徴収の理由を、救急搬送の半数が軽傷者で、6割が大病院に集中し、現場がひっ迫しているとしましたが、そもそも病院の機能分化と集約化で大病院に集中させてきたのが県や国の医療政策ではないですか。軽傷が半数というのは全国も同じ。では、6割の集中率が他より高いのか、知事は説明がありません。
そこで私は、厚生労働省にデータを求めました。大病院への集中率―全国平均は69.76%。人口同規模の京都府は75.47%。本県はそれよりはるかに低い61.3%で、全国37番目にも関わらず現場がひっ迫するのは、救急病院の医師や看護師等体制が脆弱だからではないでしょうか。
新日本婦人の会が行った選定療養費緊急アンケートに、「搬送先が決まらず1時間も待った」「緊急性の有無は素人にはわからず、医者が少ないのが問題なのに責任をすり替えないでほしい」と切実な訴え。そして「子どもは徴収の対象外にしてほしい」との声も多数です。
厚労省も「小児救急は特別だから#8000は子ども専用ダイヤルにしている」と言い、県立こども病院に伺った際も、小児救急医師は「いつもと様子が違ったらためらわず救急車を呼んでほしい」と呼び掛けています。学校や交通事故現場からの搬送も徴収すべきではありません。徴収の撤回と見直しを求め、知事の所見を伺います。
(2)救急医療の支援、医師・看護師等の確保
病院関係者は、「救急を受けるほど赤字が増える」「特に夜間は体制が取れない」との切実な声です。私は昨年9月の予算特別委員会で、「救急受入1件あたり620円~970円の県補助金はあまりに少ない」と増額を求めましたが、知事はその考えはないのか。また、県内10カ所しかない休日夜間診療所を増やす考えはないのか伺います。
さらに、人口あたりの医師数・看護師数も最下位レベルというのに、知事は「医師偏在」が問題だとしていますが、絶対数が足りないのが本質で、その認識に立って国の医師数抑制策を見直すよう求めるべきです。所見を伺います。
【知事】
江尻加那議員のご質問にお答えいたします。
初めに、県民の命を守る救急医療体制の拡充についてお尋ねをいただきました。
まず、救急搬送における選定療養費の徴収撤回・見直しについてでございます。
今回の救急搬送における選定療養費の徴収は、本県の救急医療現場のひっ迫により、重篤な救急患者を受け入れるという病院本来の役割が果たせなくなり、救える命を救えなくなる事態を回避するため、県医師会や対象病院などの関係機関と慎重に協議を重ね導入したものであり、本県と他県の状況を比較して必要性を検討したものではございません。
また、いくら救急医療体制を強化しても、県民一人ひとりが限りある医療資源を適切に利用しなければ、救急医療現場のひっ迫を根本的に改善することはできないと考えます。
本県の救急医療を守るためには、緊急性が低い患者は、とりあえず救急車で大きな病院の救急外来を受診いただくのではなく、まずは地域の診療所などを受診いただき、必要な場合には大きな病院に紹介するという、医療機関間の機能分担や相互連携を更に推進することが重要であると考えております。
こうした考えを県民の皆様に御理解いただけるよう、県公式サイト内の特設ページやSNS、県広報紙ひばりとともに配布した広報用リーフレット、医療機関や福祉施設、学校など6千を超える施設に配布したポスターなどにより、丁寧に周知を行ってまいりました。
一方で、例年、冬場は救急搬送が最も多い時期ですが、今年度はインフルエンザの感染拡大も加わり、全国的に救急医療機関が大変ひっ迫したと聞いております。
こうした中、運用開始後2か月間における近隣県の救急搬送件数を確認したところ、いずれの県も前年同期比で約6パーセントから10パーセント程度増加したのに対し、本県は3.3パーセントと小幅な増加にとどまったほか、本県の軽症等の救急搬送は前年同期比で5.2パーセント減少していることから、救急車の適正利用や救急医療のひっ迫緩和に一定の効果があったものと考えております。
このため、県として選定療養費の徴収を取りやめることは全く考えておりません。
また、小児や交通事故に遭われた方であっても、緊急性に乏しい場合もあり得るため、特定の集団を徴収対象から一律に除外するということはいたしませんが、交通事故のような場合で、救急電話相談に相談する余裕がない時には、命を守ることを最優先に、迷わず救急車を要請していただくよう、県民に一層の周知を図ってまいります。
県といたしましては、引き続き、救急医療機関の適正受診や救急車の適正利用、救急電話相談の活用について、県民にしっかりと周知するとともに、関係機関と緊密に連携しながら、本取組を適切に運用してまいります。
次に、救急病院への支援、医師・看護師等の確保についてでございます。
救急患者に適切な医療を提供するためには、重症度や緊急度に応じた医療機関での受入が重要であることから、県では、初期、二次、三次救急医療機関による救急医療体制を総合的、体系的に整備してまいりました。
このうち、二次及び三次の救急医療体制を担う地域の中核的な医療機関につきましては、緊急的な医師確保が必要なものを「最優先の医療機関・診療科」に選定し、これまで目標に掲げた医師数を全て確保したほか、県、大学、医療機関などが一体となり、「医師配置調整スキーム」による医師派遣に取り組んでおり、これらにより、県内の救急医療体制は一定の水準を確保できているものと認識しております。
しかしながら、例えば、鹿行地域のように、本来は地域で対応すべき救急患者が域外の大病院に流出していることから、地域の中核的な医療機関の体制強化を図ることが必要な地域もございます。このため、現在、神栖済生会病院の体制整備に、鋭意取り組んでいるところでございます。
一方、救急医療体制が十分であっても、限りある医療資源を適切に利用しなければ、救急医療現場のひっ迫を根本的には改善することはできないと考えております。
大病院の負担軽減をするためには、医療機関間の役割分担が必要不可欠であり、地域で受けられる患者は地域で担う観点から、市町村が事業主体である軽症患者に対する初期救急医療体制につきましても、行方市など特に脆弱な地域に対しましては、県が積極的にバックアップするなど、引き続き機能強化を進めてまいります。
また先に答弁した、救急搬送による選定療養費徴収開始も、大病院の救急負担を減らし、一刻を争う重症患者の命を救う観点からのものであり、引き続き取り組む必要があります。
なお、議員からは「国の医師数抑制策を見直すべき」とのご指摘もいただきましたが、救急医療に限らず、医療提供体制の充実にあたっては、私はむしろ、医師の総数の確保ではなく、偏在を是正することが重要と考えております。
その理由といたしましては、国の推計において、本県は、地域枠などの取組により、県全体としては2036年時点の必要医師数を達成するものの、依然として地域の偏在は残ることが見込まれているからであります。
さらに、臨床研修修了直後に美容外科に進む、いわゆる「直美(ちょくび)」が話題になっております。ワークライフバランスを重視する若手医師の増加に伴い、外科などの政策医療を担う診療科を選択する医師が減少傾向にあります。
そのような中、今定例会におきましては、医師偏在の是正に向け、修学資金貸与制度における県内医師不足地域での従事要件を地域枠と同様に見直す条例改正案を提出したところでございます。
県といたしましては、救急医療をはじめ、県内の医療提供体制をしっかりと確保するため、引き続き中核的な医療機関の医療従事者の確保と偏在是正に取り組んでまいります。
2. 子育てを支援する教育費の負担軽減について
(1)学費の負担軽減のための取り組み
【江尻】
次に、子育てを支援する教育費の負担軽減についてです。資料2をご覧ください。
知事は所信表明で「茨城県こども計画」にふれ、子どもや保護者などの意見を取り入れながら子育て支援の充実をめざすとしました。その意見が、県が行った基礎調査に示されています。
小学5年生と中学2年生の子どもたちが、「子育てのために必要なお金を配ってほしい」と県や国に要望する現状をどう考えますか?大学生や専門学校生が、「将来はのんびり気ままに暮らしたい」と答えたのは、競争教育に追い立てられ、学費のためにバイト漬け、もっと自由な時間が欲しいと切望する表れではないでしょうか。
そして、保護者は「大学就学に必要な費用」が負担だと言うのに、県は県立6学校の授業料を値上げし、議会は前回定例会で値上げ撤回を求める請願を否決してしまいました。当事者の声はないがしろです。
県は、5億円でできる県立大学校等の授業料無償化を実施する考えはないでしょうか。小・中・高校ともに制服や学用品が値上がりし、県立高校ではタブレット端末6万円が新たな負担になっています。入学支援金が必要です。卒業後の進学を支援する県の奨学金についても、給付型の拡充が求められます。
そこで、学費の負担を軽減する県の取組を求め、教育長に所見を伺います。
【教育長】
子育てを支援する教育費の負担軽減についてお答えいたします。
まず、学費の負担軽減のための取組についてでございます。
県では、現在、国が策定した「こども大綱」を踏まえ、「こどもまんなか社会の実現」を基本目標とし、子ども政策に関する多くの施策や取組を一体的に展開するための指針として、「茨城県こども計画」の策定を進めております。
児童生徒や保護者などの意見を計画に反映させるために、昨年度実施した「こども計画策定のための基礎調査」の結果からは、議員ご指摘のとおり「大学就学に必要な費用」や「高等学校就学に必要な費用」などの教育費の負担軽減を求める声が多かったところです。
このうち、「大学就学に必要な費用」については、主に、国において、低所得世帯向けに給付型をはじめとした「高等教育の修学制度」を行っており、県において周知活用を図っております。
また、「高等学校就学に必要な費用」については、高等学校等の授業料を支援する国の就学支援金制度が、2025年度から、公立・私立ともに、公立の授業料相当の11万8,800円まで、所得制限なく無償化される見通しでございます。
授業料以外の費用につきましては、例えば、県立高等学校のタブレットの購入費、中学校の部活動地域移行に伴う地域クラブへの参加費などがありますが、個人資産の取得や、受益者負担の考えのもと、基本的に保護者の負担としているところでございます。
このうち、県立高等学校のタブレット購入費につきましては、国の水準を満たす端末を低価格で提供する事業者を選定し、高校から保護者に案内するとともに、低所得世帯につきましては、県独自の支援策として、非課税世帯には県所有端末の貸与を、非課税世帯に準ずる世帯には、端末購入費の補助を行うことで、保護者負担を軽減しております。
また、中学校の部活動地域移行における地域クラブの参加費につきましては、国の実証事業における補助の活用や、活動場所に学校施設を活用するなどの対応を行っていることに加えて、困窮世帯への補助に対する国への要望やクラウドファンディングの活用検討など、保護者負担の軽減に努めているところでございます。
奨学金については、県独自の貸与型奨学金制度である茨城県奨学資金や、入学一時金制度を用意しておりますが、国の給付型奨学金と併給が可能であり、基準を満たす全ての方に制度をご利用いただけるよう貸与枠を多めに設けております。
県といたしましては、学費の負担軽減につきまして、今月に策定を予定している「茨城県こども計画」に基づき、各種施策を推進するとともに、必要な教育費の確保につきまして国への要望を継続し、その動向を注視しながら、引き続き研究に努め、保護者負担の軽減に取り組んでまいります。
(2)学校給食の質の確保と無償化をめざす県の取り組み
【江尻】
次に、学校給食についてです。
保護者が学校に払う費用のうち、約半分が毎月の給食費です。知事は、初出馬した8年前、給食費無償化の検討を公約に掲げました。当選後、私が「ぜひ具体化を」と質問したのに対し、知事は「都道府県が支援の上乗せを行っている例はない」「必要経費が年間約100億円に上る」「慎重に検討する」と答えました。
あれから8年。青森県や和歌山県、東京都が市区町村への半額補助を実施。大分県を含め県立学校で無償化も始まっています。本県でも21市町村が無償化し、県が半額補助すればすべての市町村に可能性が広がります。半額補助なら100億円はかかりません。国待ちでなく、県立学校も無償化すべきです。
ところが、予算にあるのは600万円の今年度分補正だけ。給食を出す特別支援学校など県立47校のうち、今年度値上げした学校等27校を対象に1月~3月分、1食20円の補助のみです。4月以降は予算なしでどうするのか。また値上げですか?地元の市町村立小中学校に行けば無償なのに、県立特別支援学校に行く子どもは無償化どころか値上げという事態に、知事や教育長は心が痛まないのでしょうか。
安い食材や献立に変更したり、果物を削ったりと影響が出ています。茨城県食と農を守るための条例には、「県は地産地消に関する県民理解を深め、有機農産物その他良質な県産農畜産物の給食利用の促進に努める」と明記しています。
よって、学校給食の豊かな質を確保し、無償化を求め教育長に伺います。
【教育長】
学校給食の質の確保と無償化を目指す県の取組についてでございます。
学校給食は、成長期における児童生徒の心身の健全な発達に資するとともに、児童生徒が食に関する正しい理解を得る上で、重要な役割を果たすものと考えております。
その学校給食に係る経費につきましては、学校給食法により、施設設備に係る経費や運営に要する経費は学校設置者が負担し、食材費は保護者が負担することとされております。
県内の市町村立学校及び県立学校において、この保護者負担分の食材費を無償化するために必要となる経費は、市町村立学校においては、約113億円、県立学校においては、約2億円が見込まれております。
このように、県の主導による無償化の実施につきましては、多額の財政負担を伴うことから、政策としての優先度や財政状況を踏まえ、慎重な対応が必要であると考えております。
なお、2024年5月1日時点で、県内では16市町が、管内小中学校の給食費を完全無償化しておりますが、議員ご提案のように、市町村立学校の給食費の半額を県が補助した場合は、約56億円の県負担が必要になります。
無償化の実施につきましては、各市町村において主体的に判断されるべきであり、県による半額補助につきましても、慎重な対応が必要と考えております。
一方で、給食費の無償化につきましては、現在、国において小学校は2026年度から、中学校は早期の制度化を目指す動きがあり、今後、国において法令や制度の整備や財源の整理が進められることが見込まれていることから、その動向を注視してまいります。
次に、物価高騰に係る対応についてでございます。
県では、今年度、今般の物価高騰を受け、給食費の値上げによる子育て世帯への負担を軽減するための措置として、県立学校を対象に「学校給食等物価高騰対策事業」を創設し、昨年度からの食材費の値上げ相当額分の支援について、今定例会に予算案を提出しております。
来年度以降の実施につきましては、物価高騰対策や無償化についての国の動向などを注視しながら検討してまいります。
なお、市町村立学校における物価高騰対策につきましても、学校設置者である各市町村において主体的に判断されるべきことであることから、県では、国の重点支援地方交付金を活用した対応について市町村へ案内するなど、情報共有と好事例の展開に努めております。
また、学校給食の質の確保につきましては、文部科学省より、児童生徒の心身の健全な発達のために望ましい栄養量を定めた「学校給食摂取基準」が示されており、各学校設置者においては、物価高騰の中、献立の内容を工夫しながら、本基準に基づいた適切な学校給食の実施をしているところでございます。
県といたしましては、引き続き、国の給食費無償化や物価高騰対策などの動向を注視するとともに、学校給食費支援の在り方について研究してまいります。
3. 公共交通の維持確保と高齢者の外出支援について
(1)市町村コミュニティ交通運営への財政支援を
【江尻】
次に、公共交通の維持確保と高齢者の外出支援についてです。
知事は開会日、約50分にわたる所信表明の中で、「高齢者」と言葉にしたのは1回。「本年は団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となる」と述べましたが、どんな施策を展開するかは一言もありませんでした。
一方、県議会が昨年取りまとめた交通政策・物流問題調査特別委員会の報告書は、29カ所高齢者について触れ、「買い物や医療機関へのアクセスなど日常生活に不便が生じないよう、高齢者の目線に立った公共交通の環境整備」を求めました。日本共産党が取り組んでいる要求アンケートでも、「車がなければ不便で不安だ」という声がどこでも寄せられます。
公共交通を補っている市町村のコミュニティバスやデマンドタクシーも維持確保に苦労しています。昨年度の利用者は350万人に上り、茨城空港の旅客数の4倍以上です。その350万人の利用を支える運行経費年約20億円に対し、運賃収入は5億円で、その差額15億円を市町村が負担しています。県はこれに1円も補助しない反面、空港対策には毎年10億円規模を投入しています。ぜひ、市町村コミュニティ交通へ直接の財政支援を求めますが、政策企画部長の所見を伺います。
(2)「いばらき版シルバーパス」の創設など高齢者支援を
外出支援は健康長寿につながり、交通事業者も利用者が増えれば助かります。そこで、東京都シルバーパスを参考にし、県内様々な公共交通に利用できる「いばらき版シルバーパス」を創設するなど、高齢者運賃割引補助の新しい取組について、あわせてお答えください。
【政策企画部長】
公共交通の維持確保と高齢者の外出支援についてお答えいたします。
まず、市町村コミュニティ交通への財政支援についてでございます。
地域公共交通は、住民の豊かなくらしの実現や社会経済活動に不可欠である一方で、人口減少やテレワークの普及といったライフスタイルの変化により、利用者数が減少傾向にあるなど、大変厳しい状況にあります。
このような状況の中、地域の移動の足をいかに維持確保していくかが大きな課題となっております。
このため、県では、「茨城県地域公共交通計画」に基づき、地域公共交通のあり方や方向性について、市町村などと認識を共有しながら、多様な輸送資源を総動員していくことにより、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を目指しているところでございます。
地域公共交通ネットワークのうち、主に市町村域内の移動を支えるコミュニティ交通につきましては、いわゆる「2024年問題」による運転手不足の深刻化などにより、路線バスが大幅に減便されていることから、それらを補完する公共交通としての重要性が高まっていると認識しております。
コミュニティ交通の運行経費につきましては、国から市町村への財政支援として、その最大8割が特別地方交付税で措置されているほか、地域間交通ネットワークを補完する路線の維持確保に向けた補助制度が設けられております。
また、県では、コミュニティ交通の導入やデマンド交通のAI化などに取り組む市町村に対し、その調査検討費用や初期費用などを支援しているほか、一般の車両やドライバーを活用する自家用有償旅客運送制度の見直しなど、最新の国の動向に対応するため、市町村やタクシー事業者などの関係者とワーキングチームを立ち上げ、地域の輸送資源を有効活用した新たな交通の仕組みづくりについて検討を進めているところでございます。
さらに、つくば市を中心に、隣接する土浦市、下妻市、牛久市の4市が連携して、運転手の確保、育成、管理を行うドライバーバンクや、AIによる最適な配車、ルート算出を行うAIオンデマンドモビリティなど共通のサービス基盤の構築を行うことにより、地域住民の持続可能な生活の足の確保を目的とした自家用有償旅客運送制度による新たな移動サービスの提供が、本年1月から始まったところでございます。
これらの新たな動きにつきましては、引き続き、県地域交通政策推進協議会などの場を通じ、市町村へ情報共有を行うことなどにより、先進的な取組や好事例の横展開を図ってまいります。
県といたしましては、関係者と連携しながら、これらの施策を継続的に進めることにより、地域の課題や実情に応じたコミュニティ交通の維持確保が図られるよう、市町村の取組を支援してまいります。
次に、「いばらき版シルバーパス」の創設などの支援策についてでございます。
本格的な人口減少・少子高齢社会において、高齢者などの地域住民の身近な移動を支える地域公共交通の維持確保にあたっては、地域の交通事情や住民ニーズを熟知している市町村や交通事業者と連携して取り組むことが必要であると考えております。
現在、県内すべての市町村において、地域公共交通のあり方を検討するための交通会議が設置されており、高齢者団体や民生委員などの地域住民や交通事業者とともに、県も委員として参画し、先進事例の紹介などの情報提供や助言を行っているところでございます。
また、住民の移動手段の確保のため、県では、市町村におけるコミュニティ交通の導入に対し、立ち上げ支援を行っており、現在9割の市町村でコミュニティバスや乗合タクシーなどが運行されているほか、高齢者をはじめとする交通弱者の自宅からの移動利用にも対応したデマンド交通によるサービスが多くの市町村で提供されております。
さらに、昨年より、城里町では、高齢者が水戸市など隣接市町に所在する中核病院へ通院しやすくなるよう自家用有償旅客運送制度を導入したほか、水戸県央交通圏や、土浦市を中心とした県南交通圏において、タクシー事業者管理の下、一般ドライバーを活用した新たな移動サービスの提供が始まったところでございます。
加えて、日立市で展開されている日立製作所との共創プロジェクトにおきましては、県も参画しながら、高齢者が安心安全に自宅から最寄りのバス停や駅などへの移動が可能となる次世代モビリティの導入に向けた検討が進められております。
議員ご案内の東京都シルバーパス事業につきましては、高齢者の社会参加を高め、高齢者の福祉向上を図ることを目的として、200億円を超える予算を確保し、満70歳以上の都民が、一定額を負担することで、1年間、都内の民営バスや都営交通などに乗車できるパスを発行する事業であり、関東近県では、東京都のみで実施されている取組であると認識しております。
「いばらき版シルバーパス」の創設などのご提案につきましては、実施にあたり多額の財源が必要となるほか、公共交通が発達した都市部などに事業効果が限定されやすいこと、さらに、通学利用者など他の世代との公平性の観点からも、課題があると考えております。
県といたしましては、「活力があり、県民が日本一幸せな県」を支える持続可能な地域公共交通ネットワークの構築の実現に向け、市町村や交通事業者などの関係者と連携を密にしながら、高齢者をはじめとする地域住民の移動手段の確保に取り組んでまいります。
4. 水道行政と水資源開発について
(1)水道事業経営一体化の問題点
【江尻】
次に、水道行政と水資源開発についてです。
県は「1県1水道」を掲げて約3年、市町村と協議を進め、2月26日に経営一体化基本協定を21市町村(栃木県野木町含む)と結びました。自治体数では約半分ですが、給水人口で見ればわずか3割にしかなりません。自前の浄水場をなくして市町村は災害時にどう対応するのか。命の水を守れるのか。水道管や施設の更新に国・県の補助こそ増やすべきで、広域化に反対です。
県は経営一体化で、国の交付金活用額が542億円増えるとしましたが、すべて財源措置される保証があるのでしょうか。
また、組織の集約化により人件費を94億円削減するとしていますが、ただでさえ水道技術職員が少ない中で人を減らせば、技術者の確保・育成は困難になるのではないでしょうか。
そして、経営統合から途中で抜ける場合は「協議会の同意を得た上で脱退できる」としていますが、参画市町村すべての同意が必要なのか。また、脱退時のお金の清算についても「別途協議する」とあるのみで、こうした重要点を曖昧にして市町村を参画させることは問題ではないでしょうか。以上について、知事の所見を伺いします。
【知事】
水道行政と水資源開発についてお答えいたします。
まず、水道事業経営一体化の問題点についてでございます。
人口減少などにより、厳しい経営環境にある水道事業については、スケールメリットを活かした広域連携に向け、浄水場の統廃合による全体最適化や、経営の一体化による業務の効率化、組織力の強化などについて、市町村と検討を重ねてまいりました。
この結果、先月末に21市町村と「経営の一体化に関する基本協定」を締結したところですが、その概算の効果額として、建設改良費や維持管理費の削減、国交付金の活用などにより1,137億円以上のコスト削減を見込んでいるところでございます。
このうち、国交付金につきましては、活用可能額の試算にあたり、過去の実績を踏まえ内示率を80パーセントで見積もるなど、厳しく推計を行っております。
国の交付金に関して、県では必要な予算の安定的な確保をこれまでも要望しており、広域化に必要な交付金の満額確保に向けて引き続き国と協議を進め、効果額の上積みを図ってまいります。
次に、経営統合後の雇用や給料などの処遇についてでございます。
経営統合後の市町村末端給水事業の運営体制につきましては、市町村から県への職員派遣により維持するとしたことから、現在従事している職員の雇用は継続いたしますとともに、給与など勤務条件につきましても、派遣元の市町村の関係規程が適用されますので、基本的には従来と同様でございます。
さらに、水道技術者の確保・育成につきまして、経営統合に伴う将来的な組織再編の際も、管理職などの見直しは見込んでいるものの、水道技術者は、最優先で確保に努めます。
加えて、経営統合を契機に、複数事業体のノウハウを共有するとともに、企業局の技術職とも連携し、人材育成や技術力の向上を図ってまいります。また、AI技術を活用した浄水場の運転管理の集中制御監視、管路の更新周期の長寿命化などにより、事業の効率的な運営と職員の負担軽減を図ってまいります。
次に、経営の一体化からの脱退についてでございます。
経営の一体化に向けた準備を円滑に行うため、協定を締結した市町村と県で「広域的連携等推進協議会」を設置し、今後、詳細な調整を進めていくこととしております。
調整の過程で、経営統合への参画が困難と判断した市町村は、協議会の同意を得た上で脱退することができることとしておりますが、例えば、既に施設整備を進めており、脱退に伴い当該施設が過大になる場合は、原因者である市町村に相当の負担を求めることも考えられるなど、個別事情によって対応が変わってくるため、条件を予め提示することは困難であります。このため、個別具体の案件により協議会の中で市町村とともに対応を協議していく必要があるものと考えております。
県といたしましては、引き続き水道事業の経営の健全化及び基盤の強化に向けて、市町村と力を合わせて着実に取組を進めてまいります。
(2)霞ヶ浦導水事業の見直し
【江尻】
霞ヶ浦導水事業の見直しについてです。
経営一体化の中で、霞ヶ浦導水を前提とする県中央広域水道用水の水戸浄水場の規模を、現状の54,000m³/日から108,000m³/日に2倍化する方針ですが、市町村の受水量が増える根拠はどこにあるのでしょうか。
この県中央広域水道用水について、知事は2月の会見で、昭和59年の導水事業開始当時に計画された24万m³/日と比べて水需要予測が減少し、施設能力に見合った収益が得られないので資産価値を減損するとしました。そうであるなら、帳簿上だけでなく、実際の施設規模や那珂川の水利権、そして導水事業そのものを見直すべきです。
過大な人口予測による導水事業が完成となれば、経営一体化に参加・不参加に関わらず施設維持費が市町村の負担となるのに、その見込額と受水料金への影響を示していないのは問題です。お示しください。
着工から40年。総事業費2,395億円のうち、すでに約2,000億円使いながら、2030年度の完成予定までに土浦トンネルができないことは誰の目にも明らかです。県は、「石岡トンネルさえつながれば利根川~霞ケ浦~那珂川の水のやりとりは可能」との理屈で国に通水を求め、当初計画にはない北浦への通水まで国に提案を伝えました。もはや霞ヶ浦導水が破綻していることを県も認めたことになるのではありませんか。
霞ヶ浦の環境というなら、常陸川水門の柔軟運用や耐震化、魚道の運用改善など要望すべきです。以上について、知事の所見を伺います。
【知事】
霞ヶ浦導水事業の見直しについてでございます。
まず、水戸浄水場の拡張根拠及び施設計画についてであります。
拡張につきましては、水道施設の全体最適化の検討において、県水の活用によりコストメリットがあると判断し、県水を活用する市町村が増えるため、5万4千立方メートルから10万8千立方メートルに施設能力を拡張して整備する計画としております。
次に、那珂川における水利権及び霞ヶ浦導水事業の見直しについてでございます。
県中央広域水道用水供給事業の減損会計に合わせた水利権と霞ヶ浦導水事業の見直しにつきましては、水道用水以外のさまざまな需要の可能性が見込まれますことから、現時点では見直しについて明確な方針を申し上げられる状況にはございません。
次に、霞ヶ浦導水事業完成後の負担増見込み額と県水料金への影響についてでございます。
まず、全体事業費を、2020年12月の事業計画変更で国より示された2395億円として試算した場合、県中央広域水道用水供給事業では、完成後、減価償却費が増加するものの、その後施設最適化に伴う県水転換の進展や、広域化のスケールメリットにより、それを上回る収益の増加が見込まれるため、将来の基本料金は値下げできるものと考えております。
一方、維持管理費を、国の2020年事業再評価資料で示された年間約16億円として試算した場合、将来の水需要に応じて、1立方メートル当たり5円から10円程度の負担増となる見込みであるものの、実際の使用料金の値上げは、それよりも小幅で済むと考えております。
次に、霞ヶ浦導水事業の計画の破綻についてでございます。
霞ヶ浦導水事業は、浄化や渇水対策のほか都市用水の確保を目的としておりますが、現在工事中の石岡トンネルが完成すれば通水が可能となり、都市用水の安定的な確保が期待されますことから、県として国に対し完成施設の早期の効果発現を要望しているものでございます。
また、北浦への通水につきましては、令和6年第2回定例会で霞ヶ浦導水の堅倉立坑から巴川を経由した北浦通水に関する質疑があり、県としては整備費用などの課題もあるという認識であることを北浦の管理者である国に伝えておりますが、その対応は課題の解決を含めて国において整理されるべきものであります。
いずれにいたしましても、霞ヶ浦導水事業の計画そのものが破綻したものではないと認識しております。
次に、常陸川水門及び魚道の運用についてでございます。
常陸川水門につきましては、利根川からの洪水の逆流防止や塩害の防除を目的として、1963年に国が設置した施設であり、魚道も地元住民や漁業関係者などから要望を受けて国が設置したものでございます。
現在、常陸川水門は、水門操作による霞ヶ浦の貯水容量の確保により利水としても活用されていることから、本県の利水に影響がないよう、管理者である国の責任において耐震化も含めて適切に管理がなされるべきものと認識しております。
また、魚道を含めた常陸川水門の柔軟運用につきましては、これまでも県から国に対して「利水」と「自然環境」の共存のための最適な運用について要望を行っており、引き続き適切な対応を行ってまいります。
5. 茨城空港の機能強化案(新たな平行誘導路等)と自衛隊百里基地について
【江尻】
次に、茨城空港の機能強化案と百里基地について伺います。この件について、資料3、資料4をご覧ください。資料3は県の「茨城空港のあり方検討会」の資料で、機能強化案として既存滑走路の強化や平行誘導路の確保とありますが、敷地境界線が描かれていません。
そこで資料4を作りました。
外側の青い線が、国の重要土地等調査法に基づく百里基地の特別注視区域。内側の青い線が基地の敷地境界で、真ん中にある自衛隊用と民航用2つの滑走路をはさんで、下に基地施設、上に空港施設です。
そして、自衛隊用の誘導路をくの字に曲げている平和公園と、反対側にある海軍航空隊の射撃場だった山は、どちらも民有地です。
その射撃場山に丸々かかる形で誘導路が描かれているのですから、地主にとっては寝耳に水。再び土地を奪おうというのでしょうか。概算事業費も示さず、パブリックコメントにかけるのですか?
知事は、百里における基地反対の苛烈な住民闘争の歴史と苦難をどのように認識しているでしょうか。戦後の一坪運動により、平和公園は400人近い人、射爆場山は500人以上の共有名義で、基地を両側から挟む「くさび」となって、歴史の逆戻りを阻止しているのです。
それを無視し、再び住民から土地を奪う誘導路計画は認められないという声をどう受け止めるのか。反対する住民には土地収用もあり得るのか、知事に伺います。
県担当課は勉強会で、誘導路を県と国交省でつくった暁には、「防衛省に差し上げることになる」と言いました。県のあり方検討会に参加する防衛政策局運用基盤課に私が聞き取りした際も、新誘導路を自衛隊が使用することは可能だと答えました。自衛隊は今ある民航用滑走路も使っており、新誘導路も使うとなれば、「第3の滑走路」となって防衛省の管轄下に置かれます。
戦後80年、戦争も核兵器もない世界が望まれるとき、自民・公明政権は5年間で43兆円の防衛費を計画。百里基地には最大500億円を投入して戦闘機の隠ぺい施設や分散パッドの整備、生物化学兵器に対応する施設強靭化を進める計画です。そんな軍備増強のもとで、就航誘客促進は成り立ちません。中止を求めます。
【知事】
茨城空港の機能強化案 新たな平行誘導路等と自衛隊百里基地についてお答えいたします。
茨城空港は、開港から15周年を迎え、年間約75万人に利用されるようになり、本県をはじめ、周辺各県の航空需要に対応し、観光やビジネスをはじめとした交流拡大を支える空港へと成長を遂げてまいりました。
このような中、県では、急速に拡大するインバウンド需要などをしっかりと取り込み、地域経済のさらなる活性化や利便性向上を図ることが重要であると考えております。
このため、今後の空港が果たすべき役割やその実現に向けた具体的な方策を検討するため、昨年8月に「茨城空港のあり方検討会」を設置し、議論を重ねていただいているところであります。
先般、検討会において示された議論中の将来ビジョン案では、有識者、関係機関や県民の方々などの意見を踏まえ、例えば、航空会社の安全かつ円滑な運航のため、取付誘導路や平行誘導路の確保が必要となるほか、旅客の利便性向上などを目的とした環境整備といった、様々な取組が整理されてきております。
これらは、当検討会が今後の空港が果たすべき役割を実現するために必要な取組の大きな方向性を示したものであり、この将来ビジョンが、本県の成長・発展に繋がる重要な布石の一つになると考えております。
県といたしましては、これらの取組は、将来ビジョン案が検討会から提言されたのち、航空需要などに応じ、関係者と協議しながら、国へ要望活動を行うなどして、実現を目指していくものと認識しております。
平行誘導路につきましても、国が今後の需要や必要性を踏まえ、その設置を判断するものであり、現時点で土地収用について申し上げることは差し控えたいと存じます。
なお、議員ご指摘の航空自衛隊百里基地の歴史的な認識でございますが、航空自衛隊百里基地は、1938年の旧百里原海軍航空隊の発足を端緒に、戦後農地として開放されたのち、旧小川町から誘致運動などにより設置されたものと承知しております。
また、基地反対住民においては、着工の際の建設機材の搬入を巡る警官隊との衝突や、計画用地を取得するいわゆる「一坪運動」、国の用地取得に対する無効訴訟での国の勝訴など、様々な経過があったものと承知しております。
県といたしましては、茨城空港の更なる飛躍・発展に資する、将来ビジョンの実現には、地元の方々をはじめ、県民の皆様や経済・観光団体、空港関係者などのご理解が非常に重要であると考えており、必要な取り組みを具体化していくに当たっては、ご理解が得られるよう、丁寧に取り組んでまいります。
6. 東海第二原発の再稼働問題について
【江尻】
最後に、日本原電の東海第二原発の再稼働中止を求めて知事に伺います。
原電は、昨年9月に対策工事を完了する予定でしたが、欠陥不良が発覚した防潮堤をはじめ多くの工事が未完了。避難計画も解決不可能な課題が積み上がり、福島の惨劇は「故郷を丸ごと失うのが原発事故だ」と教えています。
東海第二原発の安全性はどうか。県の原子力安全対策委員会ワーキングチームが論点に上げた230項目の審議を一通り終えるとされた2月の会議(30回目)で大きな論点が持ち越しされました。
一つは、私がかねてから指摘していた原子炉中性子照射脆化の問題です。核燃料から放出される中性子が原子炉の鋼材に当たり、粘り強さがどれだけ低下しているかを監視する試験片が東海第二は4つしかなく、これまで4回の試験で使い切りました。再稼働して5回目以降は、使い古しの試験片を再利用するとの説明に、委員から厳しい疑義が出たのです。
そこで、試験片が4つしかないのは東海第二だけ、再利用した事例もないと考えますがいかがか。原電が再三説明しても結論に至らなかった理由について、ご答弁ください。
もう一つの論点は、一昨年9月に日本共産党への内部告発で、県が初めて知ることとなった防潮堤の施工不良問題です。なぜ初期段階で発見・対策・是正できなかったのか。検査体制や管理能力のどこに問題があるのか。また、防潮堤の設計変更を審査する規制委員会の詳細な解析データを原電が示せない理由について、原電からどのように聞いているのかお答えください。
2月4日に中央制御室で爆破弁の作動試験中に火災を起こし、知事は原電を厳重注意しました。そして27日には、原子力規制委員会に要請文を出し、日本原電が原発の運転を的確に遂行する能力があることを県民に明らかにしてくださいと要請しています。
しかし、それがないことは、相次ぐ火災、労災、施工不良、そしてデータ改ざんの実態を見れば明らかではないですか。知事は「安全軽視の組織文化」と指摘しましたが、原電の管理体制や技術者の能力をどう考えているのか所見を伺います。
政府は今、「原発を最大限活用する」と原発回帰しています。その自民党の政治資金団体(国民政治協会)に、日本原子力産業協会(原産協会)の会員企業から2023年までの11年間に76億円超の献金が渡っていることが、しんぶん赤旗の調査で明らかになりました。では、その原産協会の会員企業による大井川知事の政治資金パーティー券の購入の有無についても合わせてお答えください。
以上で1回目の質問を終わりますが、答弁により再質問いたします。
【知事】
東海第二原発の再稼働問題についてお答えいたします。
まず、監視試験片の数についてお尋ねをいただきました。
東海第二発電所と同じ沸騰水型原子炉(17基)については、試験片の数を公表しているすべての原子炉(9基※)で4つの試験片が装荷されております。
※東海第二原発、女川原発2号機、柏崎刈羽原発1・3・4号機、浜岡原発3・4号機、志賀原発1号機、島根原発2号機
※4つの試験片すべてを使い切っているのは東海第二原発のみ
また、去る2月12日に開催した東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにおいては、「4つの試験片に対し、4回の監視試験を行っているが、5回目の試験はどう対応するのか」という委員の指摘や県民意見に基づく論点について、日本原子力発電株式会社から、過去に使用した4つの試験片の一部を再生して監視試験を行うとの説明があったものであります。
その際、日本原電から、監視試験に使用する試験片には、圧力容器鋼材の母材部分、鋼材の溶接部分、溶接の熱の影響を受けた部分の3種類があるが、5回目の試験では、日本の民間規格に基づき、圧力容器鋼材の母材部分のみで実施する方針である旨の説明がありました。
これに対し、原子炉材料技術が専門の委員から、「アメリカの規定では、鋼材の溶接部分の試験は除外されておらず、溶接部分については溶接欠陥がある可能性もあり、少なくとも計画に入れるべきで、今の段階で母材のみとするのは疑問である」との指摘があったものでございます。
再生した試験片による監視試験の方法については、今後、日本原電が国に申請し、審査されることから、その状況を踏まえ、ワーキングチームにおいて再度説明を受けてまいります。
次に、防潮堤の施工不良についてでございます。
そもそも施工不備の内容や原因など、計画通りの工事が実施されていることの確認は、原子炉等規制法に基づき原子力規制委員会が行うべきことであると認識しております。
また、日本原電が国の審査において必要な解析データを示せない理由につきましては、新たな工法による基礎部分の強度や施工不備のあった基礎部分が残存することへの影響などについて解析する必要があり、その解析に相当の時間を要するためと聞いております。 次に、東海第二発電所で火災が相次いでいることに対し、私から厳重注意を行った件についてでございます。
私としましては、日本原電の幹部から、これまでの火災に対し、あまり大したことではないという意識が端々に感じられることがあり、そうした気の緩みが現場に伝わった結果、今回の人為的ミスによる火災につながったのではないかと考えたことから、会社組織として安全を軽視する文化を捨て去る必要があると社長に対し厳しく申し伝えたところであります。
また、国の原子力規制委員会に対し、日本原電が「発電用原子炉の運転を適格に遂行するに足りる技術的能力を有することについて、県民の信頼が得られるような形で明らかにすること」を要請したところであり、今後の原子力規制委員会の対応を注視してまいります。
なお、日本原子力産業協会会員によるパーティー券の購入の有無についてのご質問ですが、政治資金規正法の定めに従い、公開すべきものは公開しており、引き続き、法に基づき適切に処理してまいります。
再質問
まず初めに、給食費無償化について教育長から答弁をいただきました。市町村立小中学校への半額補助には56億円、県立学校の無償化には2億円、あわせて58億円あればできるとの答弁です。ぜひ知事は、大企業に100億円プレゼントするのでなく、子どもたちに無償化をプレゼントしていただきたい。実現を求めて要望いたします。
次に再質問ですが、火災を繰り返す日本原電の管理能力と資質について知事に質問します。
知事は日本原電の幹部に、あまり大したことではないという意識があること問題だとおっしゃいましたが、私もその通りだと思います。
そして先週末、東海第二原発の現場作業員とする匿名での告発文書が、またしても私の事務所に郵送されてきました。こう書いてあります。
「2月18日、東海第二原子力発電所内、三菱重工業の作業現場の溶接機でボヤ火災が発生。本来ならすぐに消防や関係部署に報告し、正式な対応をとるべきところ、内々で処理してすませる形になりました」との告発です。すぐに原電に事実確認をしましたが、「そのような事実はない」との回答です。いったい現場で何が起きているのか。作業員はどんな思いで働いているのか。知事は、現場を見たこと、現場に行かれたことがあるでしょうか。
そこで、2点お聞きします。知事は2期8年の間に、東海第二原発を視察したことはあるか。あったとしたら何を見聞きしてきたのでしょうか。2つ目には、日本原電に原発を動かす能力や資質がなければ、当然再稼働は認めないと判断できるか。明確にお答えください。
【知事】
再質問にお答えします。訪問したことはございます。日本原電の遂行能力については、原子力規制委員会の検査、判断に任されるものだと一義的には考えております。
以上
2025年3月茨城県議会 江尻かな議員の予算特別委員会質問と答弁(大要、PDF)